リドリー・スコットの映画の中で、マイケル・ダグラスがソニータワーの円形のエレベーターから外を見ている場面があった。そのとき彼が見ていた「心斎橋」はほとんど渡る人のいない陸橋だった。十年ほど前に真下に地下街ができたときに解体され、その欄干の一部だけが飾りとして横断歩道の途中に設置されて残っている。
「その街の今は」 柴崎 友香(2009年)
 /勝手に引用
/勝手に引用![]() お話しするにはログインしてください。
お話しするにはログインしてください。
リドリー・スコットの映画の中で、マイケル・ダグラスがソニータワーの円形のエレベーターから外を見ている場面があった。そのとき彼が見ていた「心斎橋」はほとんど渡る人のいない陸橋だった。十年ほど前に真下に地下街ができたときに解体され、その欄干の一部だけが飾りとして横断歩道の途中に設置されて残っている。
「その街の今は」 柴崎 友香(2009年)
『その昔、イギリスの労働者が仕事の合間に紅茶を急いで飲まなければならないとき、受け皿に紅茶を移し、冷まして飲み干すということがあったそうです。英国通の友人から「カップに入れる量は、ソーサーいっぱいに注いだ量と同じなんだよ」と教わったときは半信半疑でしたが、実際に試してみるとその通りで驚いたことがあります。』(渡辺都「お茶の味」、p.119)
ためしてみようと思ったけど、もらって箱にはいったままのティーカップしかない!><
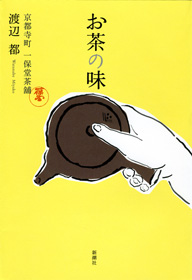
片付けが進まない。
30歳になる年、ソフトウェア会社から銀行のシステム部に転職した。副部長から
「2年間は猶予する。ただし3年目からは一切容赦しない」
と言われた。「即戦力」と気負っていた私が、どれだけ救われたことか。
数年後、部下を持つ役職になった時、上司に言われた言葉も心に響いた。
「一番の仕事は、お前の後継者を育てることだ。何もかも自分でするな。下の者に任せて育てろ。それが、お前の仕事だ」
部下を信用せず、休日出勤して仕事をこなすことが役割と思っていた。青天の霹靂ともいうべき言葉だった。
転職や移動を機に精神的な安定を崩し、受診に来る人は少なくない。そんな人たちには、この二つのアドバイスを伝えている。
薬よりずっと効き目がある。
新聞投稿欄、精神科医から
「居間兼書斎は長方形の広い部屋で、三方の壁面をおびただしい数の書物が埋めている。革表紙の匂いを立てる書物がぎっしり詰まった棚が段をなして重なり、天井に達しているのだが、第四の壁だけは、普通の居間と同様に、大きな暖炉が切ってあり、マントルピースは頑丈な樫材、火格子の鉄枠が光輝を放ち、暖炉の上には、いまはこの家の名物になったサーベルが二本、ぶっちがいに吊るしてある。これは若き日のリチャード・クイーンがドイツに留学中、ニュルンベルクのフェンシングの教師から贈られたものなのだ。広い室内のあちこちで、いくつかの室内灯がまたたき、安楽椅子…[全文を見る]
今の家を建ててから十八年になる。
私も当時は今より十八歳も若かったから(あたりまえだ)、断然、洋風の家にあこがれて、日本間なしの徹底的な洋館を造って得意になっていたものである。
(高峰秀子「コットンが好き」から「小引出し」)
1983年、60歳で「(あたりまえだ)」のセンスってハイカラだなあと思った。
僕は6歳から11歳の頃までニューヨークに住んでいたのですが、日本に帰って来た時にはカルチャーギャップを感じました。
たとえば、学校で第二次世界戦争について教わることについても、日本とアメリカの教え方は全く違います。
僕はアメリカで最初に学んでいたので戸惑いがありました。
また、中学校の頃いじめられたことがあったのですが、先生に「やめさせてください」と言っても先生達は何もしてくれず、その時もアメリカと日本は違うと思いました。
アメリカでは、どんなことがあってもとにかく自分の意思を伝えないとダメ、周りの大人に言ってわかってもらってそれが改…[全文を見る]
上司へ報告するとき、楽観的な私の口グセは「大丈夫です!」。
しかし、次の日も下振れ……
そしてある日、「明日は計画通りいきそうか?」と聞かれたときでした。
いつものように「大丈夫です!」と返した私に対し、上司はこう言いました。
「佐藤くんの大丈夫は信用できないから、これからは大丈夫禁止。全部数字で話して」。
これがなかなかツライ。口グセはなかなか抜けず、つい出てしまうのです。
その後つい大丈夫が出てしまうと、その度に本気で怒られ、そのあとの説明がうまくいかない。
ただ、禁止令が出たことで、私も数字での原因究明に徹するようになり、
…[全文を見る]
これは「大学 再入学」でググって出てきたものです。
似たようなことを定年後も同じ会社の嘱託で働いている研究者の人に言われたので貼りました。
まあ、会社組織には年齢に応じたペースというか階段が用意されてるのでそれに合わせていかねばならぬってことで。
それが手に職系と少し違うところなんじゃないですかね。
と、1段目で踏み外した私が言ってみる。
20代で社会に入門、30代でチャレンジ、40代~50代で社会を動かし、60代で監督、70代で隠居。
「一切の音楽がクラウドのような方法でタダになったら、逆に、きっとお金を払って自分のところに置いときたいと思う人が出てくるんじゃないか? この前、そんなふうに考えたんです。ただ、現実には、シェアするのがヘタになっているような気もしていて……。やっぱりミュージシャンをやってると、権利の問題ってすごく面倒くさいし。いったい僕らの何を守ってるんだろう?って、ミュージシャンの側からもわからなくなることって、たくさんありますよね。“僕の曲でよければ、どんどんサンプリングして新しいもの作ってよ”って僕は思うし……いや、それでほんとにひどいもの作ったら『やめてよ』って言うけど(笑)、いいものを編み直してもらえるんだったら、うれしいし。だけど今はそういうところに“俺の作ったものだから金よこせ”っていう気持ちが乗りすぎてるような気がして……フェアじゃないっていうか」
後藤正文
問題は過去を克服することではない。後になって過去を変えたり、起こらなかったりすることはできない。過去に目を閉ざす者は結局のところ現在にも盲目になる。非人間的な行為を記憶しようとしない者は、再び(非人間的な行為に)汚染される危険に陥りやすいのである。
(リヒャルト・フォン・ワイツゼッカー「荒れ野の40年」演説より)
全国で見ると、激増!てなことではないようなのですが、京都は環境が良いのか、ニュースになるくらい増えてますね。
夏になると、川遊びに来た人たちが噛まれたという報告もちらほら…
かなり噛む力が強いので、危険なんだそうです。
見た目ゆる~い感じなのですが、動きも素早いとのこと。
トキと違って捕まえて剥製云々の需要は低そうですので、このまま見守るしかないのでしょうね。
生めよ増やせよの自治体もあるようなので、難しいもんだいですね(´・ω・`)
トキはかつてはありふれた鳥で、田畑の作物を荒らすとして忌み嫌われ、乱獲の対象となった。ところが佐渡島にわずかに数十羽が生息するだけになると突然、その優雅な姿がひとびとのこころを捉え、二〇〇三年に最後の日本産トキが死亡すると国じゅうが悲しみに包まれた。
残酷な世界で生き延びるたったひとつの方法 by 橘玲
たるさん情報によるとオオサンショウウオは逆パターンになる恐れがありますね。
内田「コピーライトがうるさく言われ始めたのは80年代からなのかな。ミュージシャンや音楽を愛さない人間が音楽ビジネスを仕切り始めて、状況がガラッと変わってしまった。たとえば著作物に歌詞を引用する場合、いちいちJASRACに許可を得なければなりませんよね。 すると人は手続きが面倒だから語ることをやめてしまう。語られる機会を失った文化が発展していくとは思えません」
贈与とお布施とグローバル資本主義 鼎談:内田樹×釈徹宗×後藤正文
戦後民主主義を代表する政治学者丸山眞男の研究室を全共闘が封鎖した時、丸山眞男がこんな暴挙はナチスもやらなかったと言ったのは有名な話だ。ぼくたちは、その話を戦後民主主義の知識人は、いざ問題が自分におよんでくるとうろたえるという話として受け取った。たぶんぼくらは三島由紀夫のなかに戦後民主主義的知識人や大学当局がもたない誠実さを見ていたのだ。
『思想としての全共闘世代』小阪修平
村上春樹さんの『風の歌を聴け』は現代アメリカ小説の強い影響の下に出来あがったものです。カート・ヴォネガットとか、ブローティガンとか、そのへんの作風を非常に熱心に学んでゐる。その勉強ぶりは大変なもので、よほどの才能の持主でなければこれだけ学び取ることはできません。昔ふうのリアリズム小説から抜け出さうとして抜け出せないのは、今の日本の小説の一般的な傾向ですが、たとへ外国のお手本があるとはいへ、これだけ自在にそして巧妙にリアリズムから離れたのは、注目すべき成果と言っていいでせう。
丸谷才一 昭和54年 第二十二回群像新人文学賞「風の歌を聴け」選評
ツングース型のエヴェンの場合、鞍は馬のものとかなり違う。木の骨組みを毛皮の袋で覆い、トナカイの毛を一杯に詰めたもので、自転車やバイクのサドルのようにも見える。これをトナカイの肩の上あたりに装着し、やはり右手に杖を持って、サヤン型とは逆にトナカイの右側から乗る。鞍が幅広いので、またがるというより、トナカイの肩の前に脚を出して座る感じだ。鐙がないため、両脚がぶらぶらしていて何だか不安である。座る位置が前寄りなので、落トナカイする場合は横にずり落ちるのではなく、前につんのめる感じになる。
中田篤「トナカイ牧畜の歴史的展開と家畜化の起源」高倉浩樹編著『極寒のシベリアに生きる トナカイと氷と先住民』新泉社、2012年、p59。
「ぼくは…」彼の車にはCDの聴けるステレオがあったが、いつもはCDを入れていなかった。一人で運転するときは仕事をし、電話をし、口述をしていた。疲れていて目を覚ましていたいときにはラジオをかけた。しかし、昨日のコンサートの後で、彼はバッハのモテットを録音したCDを一枚買っていた。彼はそれをかけた。
ふたたび、音楽の甘美さが彼をとらえた。いまではテクストも部分的に聞きとれた。「あなたはわたしのもの、わたしはあなたにすがり、わたしの光であるあなたをけっして心から去らせません」ーーそんな言葉を口にしたことはなかったが、妻を愛し、妻も自分を愛し…[全文を見る]
歴史の初期の段階では、人間は事故を周囲の環境と区別していない。動物界・河川・山脈・森、もろもろの自然現象は、まるで人間と「対等」であるかのように存在している。(中略)人間以外のすべての動くもの、ざわめく音をたてるものもまた、人間の空想の中で、自分の意志によって行動することができ、感ずることができるのである。生き物の絵とか、かげとか、その一部分――たとえば、抜け落ちた毛でも――とかはその生き物そのもののかわりになることができ、そうしたもので示されているもとの生きものへの必要な効果を及ぼす手段となり得るのだ。ヘラジカがほしい、それなら、岩にその絵を描け、そして「殺せ」、それ以上のことは、いうなれば単なる技術の問題なのだ。
В.А.トゥゴルコフ/著, 加藤 九祚/解説, 斎藤 晨二/訳 『トナカイに乗った狩人たち 北方ツングース民族誌』刀水書房、1981年、p161
【10月20日】
「かなしくて、かなしくて、とてもやりきれない」と30年以上前に歌ったアーティストが死んだ。自殺である。
『やりたいことがもう何もない』と遺書だか、知人に宛てた手紙だかにあったそうだ。
鬱だったのだろう。それは分かる。とてもよく分かるのだ。
私だってこれまでの人生で、鬱状態に陥ったことがなかったわけじゃない。死を身近に感じたことだってある。しかし、それでもなんとかやってきた。
亡くなったアーティストは62歳で、若い頃からずっと世の中に知られた存在だった。だからこそ、自らのあり方を常に自分に問いかけざるを得なかったのだろう。そ…[全文を見る]