『とりつくしま』東直子
あらすじを読んで、短編なら読みやすいな、と購入。
亡くなった人が、現世のモノにとりついて、のこった人を見守る11篇の物語。
きっと、その時々でお気に入りは変わってくるのだと思います。
私のお気に入りは「トリケラトプス」と「マッサージ」でも、「レンズ」もいい。「青いの」はつらすぎた。
私ならどうする?どうなる?と自問自答をしてみたりして。
きっと、大切な人が、あなたがいなくてもなんとかやっているよ。ということが分かれば本当にいける気がする。そんな作品。
これ、文庫本になったのが、2011年3月15日でした。きっと、“あの日”の前と後ではまた異なった取り方になるのでしょうね。
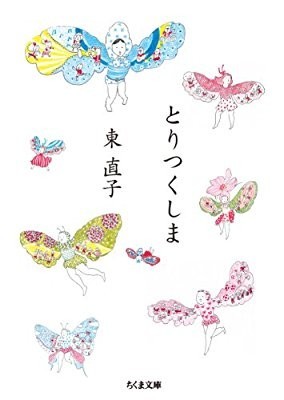
![]() お話しするにはログインしてください。
お話しするにはログインしてください。
読了のことを語る
読了のことを語る
尾瀬あきら『どうらく息子』第一〜十八集(完) 小学館
落語の世界に飛び込んだ関谷翔太を中心にした群像劇。完璧。おもしろかった! たった十八巻で終わった。あんなに、みんなに色々あって、完全に群像劇なのにラストのシャープさに驚きました。題材が落語というのも生きていて、日常触れているロジックとは違うロジック、違う文体ですっすっと物事が動いていって、どの人の「サゲ」にもドキドキしどおしの全十八巻でした。読んだ次の日、道を歩きながらふっと彼ら彼女らのことを思い出して泣いてしまった日もありました。こんなにはまっているにもかかわらず書店でタイ…[全文を見る]
読了のことを語る
5月
・東山彰良『さようなら、ギャングランド』
・いとうせいこう、奥泉光『漱石漫談』
・ 石原 千秋、小森 陽一『漱石激読』
・夏目漱石『明暗』
・村上春樹『騎士団長殺し』
5月はそんな風にして終わりました。「美禰子が三四郎を好きになるわけない」みたいな話が「漫談」でも「激読」でも出てくるんですが、そうかなあ、美禰子がちょっかい出したんじゃないかなあ、などと思いながら楽しく読みました。6月は少しさわやかなものを読みたいです。
読了のことを語る
「私の「漱石」と「龍之介」」著者:内田百閒
既に亡くなった方の思い出を語る、その語りの中にも時間を経て、ご本人の老いもあって、記憶の欠けがそこここにある切なさ
誰かが誰かを語る時に、ふっと立ち上ってくるその人の姿と言うのが、何か一瞬一緒に幻を見ているような気持ちになる
時々差し挟まれる「地震でなくなった」「空襲で焼けてしまった」の言葉や、町や人の描写から、急にこの中にいる人々が遠のくのが何とも言えない気持ち
読了のことを語る
「虞美人草」夏目漱石
読了のことを語る
「夏目漱石を読みなおす」
小森陽一
・難しかったけど、面白かった
・小説読んでもわからないはずだわと思った
・文学論と、それを著すに至る歴史的背景の解説がとても面白かった
・ゼ とかで学べばよかった
読了のことを語る
『プラハの墓地』
初エーコだったんだが、めっちゃおもしろかった!
個個人が持ってる偏見がどのように煽られ、いわゆる最終解決に向かっていくのか、を、あらゆるものに対する憎悪と偏見を全身の毛穴から吹き出してるような主人公が、自分の脱落した記憶を追いながら語る物語。主人公以外はほぼ全登場人物が実在した人々。
偽書作りが得意な主人公は、個個人の偏見を煽り利用することによって充分な資産を蓄えることを決意し、歴史の裏で、あらまほしい歴史を仕立てていく。
これものすごく「今」の話。嫌○、みたいなものを放っておくとどこに向かっていくか、と、その動きの裏にあるものは実際は何なのか、というのがよく描かれてる。歴史の話なのでそこは難しいけれど、でも読み物としての体裁をきっちり押さえて進んでいくので、ぐいぐい読んでしまう。
ほんと、「今」についての話。
読了のことを語る
4 月
・マイケル・シェイボン『ユダヤ警官同盟』
・ティモシー・ヴァースタイネン&ブラッドリー・ヴォイテック『ゾンビでわかる神経科学』
・架神恭介&辰巳 一世『よいこの君主論』
・ジェフ・ポッター『Cooking for Geeks 料理の科学と実践レシピ』
・サイ・モンゴメリー『愛しのオクトパス 海の賢者が誘う意識と生命の神秘の世界』
・臼井隆一郎&高村忠明編『シリーズ言語態4 記憶と記録』(再)
・東山彰良『ラム&コーク』
マイケル・シェイボン『ユダヤ警官同盟』、今頃読んでとってもおもしろかったので、この著者の本を続けて読もうと決めたのにそのことを今の今まですっかり忘れていました。よかった、ここに書き込む習慣にしていて。「読了」キーワード、とても便利です。
読了のことを語る
『コンビニ人間』村田沙耶香
・芥川賞と直木賞の違いがなんとなくわかってきました。この作品は直木賞ではないなと、知ったかぶったようですが、肌で感じました。第155回芥川賞受賞作。
・気持ちが悪い、というのが率直な感想です。地元の友達の旦那らは何なの。でも白羽さんはただのろくでなしだと思う。それが良かったのかな?わからないけど、恵子がコンビニで働くに至ったのにはちゃんと理由があったんだなと思える結末は良かったです。
・義妹があんまりにも正しい人でびっくりした。あれだけはっきりしてれば小気味良いとも思った。妹は気の毒に想った。
・コンビニの人たちの変わりようとか、ぐいぐい来た。私にはとっつきにくそうだったけど、おもしろかったです。
読了のことを語る
『明日の食卓』椰月美智子
・のっけから恐怖でぞわっとして、なんで私これリクエストしたんだっけ?と一度本を閉じました。『12歳』の著者だとしか認識がなかった、この方の著作を読むのはこれが初めて。
・なんていうか…こういうのを、小説で読むんだ…留美子の家庭の荒れる描写がいたたまれず。こりゃ留美子だろと踏んだらまさかの第三者登場で、こういうオチ!?と釈然としないのでした。そんなにこの日本にはイシバシユウくんが存在するんでしょうか。
・菜々、怪しいと思ってたんだよね。あすみも何でもかんでも話すんじゃないよと思ってたら案の定。そんなの菜々がセン…[全文を見る]
読了のことを語る
3月
・東山彰良『罪の終わり』
・ロラン・バルト『物語の構造分析』(再)
・小川さやか『「その日暮らし」の人類学』
・丸山正樹『漂う子』
・ミラン・クンデラ『カーテン』
・デイヴィッド・ゴードン『二流小説家』
・中島義道『「時間」を哲学する』
・金子兜太『他流試合 俳句入門真剣勝負!』
『他流試合』は新しく文庫で出てたのを昨日新幹線で読みました。おもしろかったよ! ところで『罪の終わり』を読んで何かひらめいてロラン・バルトを引っ張り出したはずなのに、バルト読んでる最中にそのひらめきをすっかり忘れた……というのを今書きだしてみて気づきました。『流』を読み直せば思い出すかも。大したことじゃないはずなのだけど。
読了のことを語る
「活きる」余華
・日本軍撤退から、国共内戦、文革、現在を生きる一人のお話
・文章は平易で、主人公は自分を「平凡」というのだけれど、一日置いてじわじわくるかんじです
・確かに映画向き、観てみたいなぁ
読了のことを語る
「流」東山彰良
・サービス精神満載。一つ一つのエピソードはアジア・台湾映画でよく観る切ない、ほろ苦い、チンピラでいっぱい。街もここもそこも映画に出てくる有名所で、作者は台北で生まれて育っているとはいっても、ある程度“わかりやすく盛り上がる場所”を選んで設定しているのかなぁと思いました。語り口も瑞々しくて、散りばめられた…というよりも、思いがけないところで絶妙に落としてくるユーモアもよかったです。
・エピソードがてんこもり過ぎ、語りが面白過ぎ、こういうところにこんなにボリュームを持たせて、このお話は一体どこへ行くのか?という疑問にハラ…[全文を見る]
読了のことを語る
「仁義なきキリスト教史」架神恭介
・キリスト教史を成立から第二次世界大戦直前まで、仁義なき風に描いたエンタメ作品
・正しいかどうかは別として、思いもしなかった組合せや視点から構成されるお話が面白かった。こういう内容の専門書を読みたいなぁと思いました。でも、難しいんだろうなぁ。
・後半は駆け足になっている感は否めませんが、これ以上多岐にわたって長々と描こうと思ったら、それはマンガにした方がいいんじゃないかなぁ。面白かろうなぁ!
読了のことを語る
「屋根裏の仏さま」 ジュリー・オオツカ
・いつもいつも声をひそめて、顔を寄せ合うようにしてしか、心のうちを語れなかった時代があったんだなぁ。それは、少女だったから、妻だったから、そして日本人だったから…と、理由は変わっているようで変わっていない。それ以外になれない理由で、そうせざるを得ないということ。
・悲しい、辛い場面よりも、そういう中でふと語られる優しい記憶に涙が滲みました。
・アメリカの人だって忘れたかったろうなぁ。それを掘り起こし、見つめることを、今も、どの国でもしなくちゃいけないなぁ。
読了のことを語る
村上春樹「色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年」
前から読みたかったんだが昨日夕方買ってきて半日で一気に読んでしまった
文庫にしては厚い方だったが引き込まれて
え?そこで終わるの?どうなるか気になる
しかし、これは恋愛小説じゃないから、そこが重要なんじゃなくて主人公が過去、自分に起きたことの謎を解明する、その過程が大切なんだな
「自分が見たいものを見るのではなく、見なくてはならないものを見るのよ。」
と主人公の恋人は言うが、それがキーワード
結局すべてが解明されるわけではないが彼を変えてしまったトラウマの理由を探る自分再生の旅
い…[全文を見る]
読了のことを語る
「耳鼻削ぎの日本史」清水克行
・耳削ぎ鼻削ぎという野蛮で残酷な行為が本当に?本当ならどうして?いつ、誰の命令で?行われていたか
・同様にわかりやすく、親しみやすい描き方で古代から江戸時代までの耳削ぎ鼻削ぎの変遷が語られています
・「各種資料の扱われ方」とか「◯◯史を研究する◯◯さん」とか、研究者のお仕事周りのことがちらほら書いてあるのも面白いです
・秀吉の朝鮮出兵についての最近の見直し意見について、短いけれど厳しく反論しています。時代の要請で歴史、事実が曲げられることに言及されるところが、これもまたこの時代が生んだ一文なんだなぁと思ったり。
・古代から明治維新までのアジアにおける日本の変遷がさらっと書いてあって、あぁ、そこのところが読みたいのだけどなぁ、何に書いてあるのかなぁと思いました
読了のことを語る
「日本神判史」清水克行
・残酷に思える湯起請、鉄火起請が室町期に多用された理由を探る。資料の引用は少なめで、読みやすい。データも必要最小限でわかりやすい。
・昔の歴史書には、その当時の歴史感(学問とか宗教とか政治)が反映されていると聞くけれど、それらを覆したはずの半世紀も前ではない歴史学(つい最近まで教科書に載っていたようなもの)も、当時のものの見方に制約や影響を受けているのだというのが、そうかー…と。
・強権を発動は、絶対権力ではなくて、不安定な権力によってなされる場合が多い。また、一見「素朴に神意を求めている」ようでありながら、そこには様々な計算や駆け引きがある。権力者も民衆も同じ人間なんだなぁとも思いました
・作者の熱意以上に探究が「とっても楽しい!」という様子が清々しいです
読了のことを語る
2月
・ミシェル・ウェルベック『プラットホーム』
・フィリップ・K・ディック『アジャストメント』(再)
・臼井隆一郎『アウシュビッツのコーヒー コーヒーが映す総力戦の世界』
・ダニエル・ドレズナー『ゾンビ襲来 国際政治理論で、その日に備える』
・アントニー・ワイルド『コーヒーの真実 世界中を虜にした嗜好品の歴史と現在』
今月は石黒正数『それでも町は廻っている』が完結しましたので、それを読み返すのに忙しかったです。終わっちゃって、晴れ晴れと寂しい気持ちです。あと、コーヒー本は一通り読んでような気がするので大分気が済みました。
読了のことを語る
ダニエル・ドレズナー『ゾンビ襲来 国際政治理論で、その日に備える』白水社
「(略)『ホントは、ゾンビなんかいないのよ』と私を安心させてくれた娘、ローレンに」という献辞で始まり、「『国際政治の理論』の著者であり、私の専門分野の大権威であるが、実のところ実際に会った事はないケネス・ウォルツに対しては、ひとこと言っておきたい。マジで、すいません…」という謝辞で終わり、155 頁の本文に対して 50 頁の訳者解説と 33 頁の注がつくこの本が「おもしろかった」ということはとりあえずおいといて、私にちょうど良かった! 「ゾンビは嗜む程度」という私に大変ぴったりで、「ああ、もっとゾンビ映画見よう!」と思えるという、とても素晴らしい出会いでしたの。
 /読了
/読了


