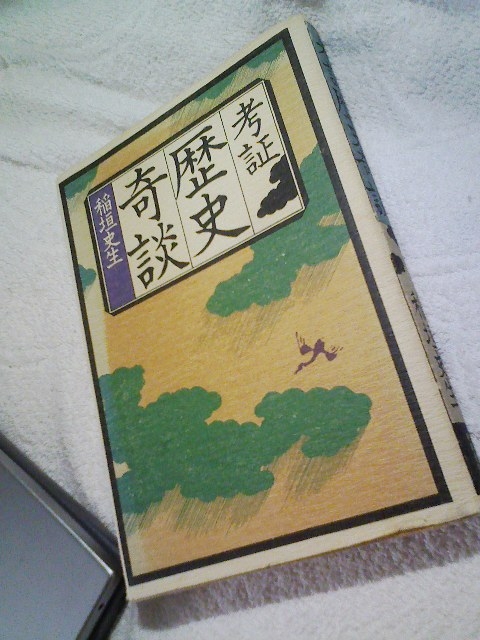『洋梨形の男』 ジョージ・R・R・マーティン(著) 中村融(編訳) 奇想コレクション 河出書房
基本ホラー風味の、ファンタジーだったりユーモアだったりSFだったりする短編集。同著者の本は数冊読んでるんだけども、ともかく筆力がすごい。においまで感じられそうで、特に表題作は、途中からずっと総毛立ちながら読んでいた。そうかと思ったら、ジョナサン・キャロルの『我らが影の声』みたいな恐ろしさの話もあるし。
ラストの『成立しないヴァリエーション』、わたしは大好きで同居人は大嫌いという正反対の反応を引き出したある映画を思い出した。同居人があの映画をなぜ嫌いなのかわかった気がした。
![]() お話しするにはログインしてください。
お話しするにはログインしてください。
読了のことを語る
読了のことを語る
西尾維新「化物語(下)」
「つばさキャット」にも、かろうじて撫子出てきたよー。
ひたぎが、なんだかかわいく見えてきた。
今回のエピソードは、やり過ぎというか出来過ぎな気がする。あいかわらず、神原とのやりとりは面白くて、ついニヤニヤしてしまうけど、しばらくこの世界はいいかな…
次は、囮読むぞ(の前に、アニメのほう見たい)。
読了のことを語る
『お呼びだ、ジーヴス』P・G・ウッドハウス(著)森村たまき(訳)国書刊行会
これの前に読んだクリスティにも「貴族と執事」のスケッチみたいなのが満載だったんで、読んでて最初、既視感が(笑) それでなくともある意味ではマンネリのおもしろさみたいなのが醍醐味だし。
しかし今回はバーティー出てこないのと、舞台の小説化ということで、じゃっかん雰囲気違ったです。日本で言うと、吉本新喜劇みたいなのを小説様に文章で書き起こしたような、というんだろうか。
最後の短編のせいで、よけいジーヴスのバーティーに対するSっぷりが光っとったわ。なにこのビルへの扱いの違い(笑)
『ブリング・オン・ザ・ガールズ』の抜粋もおかしかったんで、年内ジーヴスもの全訳終了の次は、そっちの訳もぜひぜひお願いしたいです。
読了のことを語る
The Secret of Chimneys by Agatha Christie
彼が彼女を口説くところで彼が誰かはわかったのだけど、焦点になってる誰が彼かはわかんなかったー。ちらと思いはしたけど、でもあの人のおすみつきならだいじょうぶかと思うじゃねえか、というくらい渋いスコットランド・ヤード。
しかしクリスティは時折とんでもなくスーパーマンを書いてしまうことがあるわいね。これ、Big Fourのポワロ並みかも。
読了のことを語る
読了のことを語る
宮部みゆき『孤宿の人』
ここ何年か宮部みゆきは短編ばっかり読んでたので、久しぶりに長編を読もうと思って買った……ら。
とりあえず、この話を「感動の結末」のひとことで片付けた奴。あとで職員室にいらっしゃい。
確かにラストは感涙モノだけど、そこまでの過程がさあ! 悲しすぎるじゃないのー!(おあんさんが……おあんさんがー……( TДT))
読了のことを語る
「第二音楽室」佐藤多佳子
聴くのは大好きだけど、演奏や歌は苦手だから、ついていけるかなぁと思ったけれど、心配無用でした。「音楽」というガジェットはあるけれど、彼女たちが感じている思いは、誰もが経験してきた青春のそれ。演奏というかけがえのないひとときは、青春そのものを表しているんだなぁと思った。
個人的に、男子が声変わりしていく時期って未知の世界で、女子校だったし、「デュエット」とか「FOUR」のドキドキした感じがうらやましくもあり。落ちこぼれどうしが練習場所(=秘密基地)として「第二音楽室」で過ごすうちに連帯感がうまれて、かといって…[全文を見る]
読了のことを語る
「トッカン」高殿 円
展開というか、構成的には「図書館戦争」あたりのイメージ。サラサラ読み進められるお話だけど、半ばあたりから、ぐー子が自省していく姿はけっこう重たくて、自分でも考えさせられた。
それにしても、徴収官って大変なお仕事だなぁ。警察以上の捜査権限が与えられていることも初めて知った。一方で、払いたくない人たちの金隠しへの執着はむしろ笑える。払いたくないって気持ちもすんごい分かるんだけどね。。。
すでに刊行されている次作では、いよいよ商工会が出てくるらしい。
ちなみに表紙は、武士道シリーズの長崎さん。かわいい。
読了のことを語る
『黄金の壷/マドモワゼル・ド・スキュデリ』 ホフマン(著) 大島かおり(訳) 光文社古典新訳文庫
訳者解説にある
>「頭がくらくらする」ほど美しくて、おかしくて、グロテスク
というの、『砂男』や『くるみわり人形とねずみの王様』を読んだ時に感じたそのままズバリ。あのときわたしは「乱歩みたい」と思ったのだけど。
今回の『黄金の壷』は高階良子のファンタジーものを思い出した。『マドモワゼル・ド・スキュデリ』は、ルイ14世王宮に伺候する73歳の老嬢作家による推理もので、一気に読んでしまった。残り2編の『ドン・ファン』と『クライスレリアーナ』については、音楽専門に学んでらっしゃる方の意見をうかがいたいところ。オペラに興味がないのだが、『ドン・ジュアン』を見てみたくなった。
総じてみると、やっぱりなんかわたしには、この人乱歩を感じさせられてしまう。
読了のことを語る
“Rosa Parks: My Story” by Rosa Parks with Jim Haskins (Puffin Books)
アメリカの公民権運動を拡大化させたバスボイコット、そのきっかけとなった女性運動家の自伝。
キング牧師やマルコムXなどへの言及もあり、おもしろかったし、公民権運動の大きな流れがつかめてよかったんだけど、同時に、
非暴力での運動を貫こうとするとき、シンボルとなる被害者の弱々しさ(女性であること)、「それ(この場合黒人であること)」以外では一点の傷もないクリーンさの求められ方、というのが、加害者側だけでなくサポートする側からも強く求められるという現実に、なんかたまらん…[全文を見る]
読了のことを語る
「カラット探偵事務所の事件簿1」乾くるみ
日常謎。ちょっと都合良すぎる気もするが、乾流最後のオチが楽しみで読んだ。
「え、そんなの?」とは思ったけど、やっぱり最初から読み直してみたくなるなぁ。
読了のことを語る
『江戸役者異聞』 山本昌代(著) 河出文庫
十年単位の積み本消化。
鏡の中の己の姿にしか興味を持てぬ三代沢村田之助が、人気の絶頂で脱疽に犯され四肢を失い、一人に戻るまで。
……これ、よしながふみが好きな人は絶対好きだと思う。読み終わってから頭の中で反芻してたら、よしながふみの絵とコマ割りで浮かんできた。
読了のことを語る
『始まりの場所』 アーシュラ・K・ル・グィン(著) 小尾芙佐(訳) 早川書房
わたしにしては一気読みに近いスピードで読んでしまった。以前はほんとル・グィン苦手だったのだが。
途中で、「あ、これはピーター・ジャクスンの『ブレインデッド』だ」と思った。
始まりの場所は、いつかは出て行かねばならない場所なんだ。
読了のことを語る
『残酷な童話』 チャールズ・ボウモント(著)
いろんな種類の短編が載ってるんだけど、わたしはちょっとブラック・ジョーク気味のが好きだった。
読了のことを語る
『若様組まいる』畠中恵
・明治20年、江戸を知らない元大名家ご子息の青春群像もの。シンプルでかわいい。
・中高生にいいかも。江戸明治の東京の地図がついてるともっと楽しいかも。
・「アイスクリン強し」と比べると、外伝っぽいかな。
読了のことを語る
J・M・スコット『人魚とビスケット』(追っかけ読了シリーズ)
・序章の意味ありげな新聞広告でぐっと作品世界に引き込まれるかんじです。
・中盤は、序章のことを忘れちゃうくらいの異世界冒険譚です。
・最後、満を持しての登場から急展開。面白いです!
あとはスタコメにちょっぴり。
ただ、そういう時代とはいえ人種差別がベースになっているのが辛いなぁと。語り手もサラリーマンなわけですが、家にはメイドがいたり、休暇はヨットで過ごしたりと、イギリス市民階級の人間で。今の私が読んで「普通の人」って思う人が主人公の小説が登場するようになったのって、ごく最近のことで、画期的なこと革命的なことだったのかなぁと思いました。
読了のことを語る
愛子とピーコの「あの世とこの世」
オカ板まとめスレみたいなものを予想して図書館で借りてきたけど、タイトル詐欺だった。
精神世界とオカルトについて書いた本かと思ったら、不思議話を枕に話は始まったけれど、
江原の思い出 →江原への疑念 →江原批判 →社会批判 →戦後教育批判 →女性批判
と、いつの間にか桶屋が儲かりだし、女性と母親と若い女&その子供たちをひたすらこき下ろすという意外な展開に。
×2の佐藤愛子は離婚するなんて我慢が足りないと言い切るし、ピーコはピーコで
「相手の立場に立ってみてあげる力がないのかしら」
と熱く語りながら一貫して妻…[全文を見る]
読了のことを語る
「おばさん未満」酒井順子
・細かな「おばさん未満」の悩みあるあるはもちろんですが、「おばさん」が世の中で、或いは人の人生、寿命の中でどの位置にいるのかという話が面白かったです。
・でも、こんなには「若さ」「美貌」に思い詰めたり、人に辛辣なまなざしは向けないなーと思って気がついたのですが…。やっぱり、昔からキレイだった人の方がこだわるよね。「未満」でもがく人は、それなりに自負心がある人たちなわけで。持てる者の喪失への不安と苦悩だよねぇ〜、とも思っちゃうわけです。
・で、既にショートカットの私は勝ち組だな!と。未満でもないしな!
読了のことを語る
『マンディアルグ短篇集 黒い美術館』 生田耕作(訳) 白水社
図書館で背表紙と目があってなんの予備知識もなく借りたらば、なかなかのフランス的エログロ小説であった。
短篇五つの内、ラスト三つが本来の短篇集『黒い美術館』に収録されていたもので、前二つは日本で独自に訳者が選んだものらしい。……すみません、ラスト三つがいっそうエログロでおもしろかったです。江戸川乱歩と『家畜人ヤプー』の間くらいのレベルかしらー。
読了のことを語る
『とうに夜半を過ぎて』 レイ・ブラッドベリ(著) 小笠原豊樹(訳) 河出文庫
すごく好きな話と胸くそ悪くなる話と、両方が入ってた短編集。非ヘテロに関する話もあり。
ラストの短編、あれが締めで、すごくおだやかな気持ちになった。
ブラッドベリは若々しいな。
 /読了
/読了