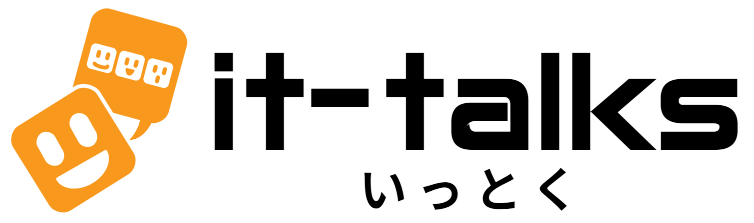いずれにしても神様は何もしてくれやしない。
でも、それは神と呼ぶにはあまりにもちっぽけな力しか持たないまなざしが、いつでもともちゃんを見ていた。熱い情も涙も応援もなかったが、ただ透明に、ともちゃんを見て、ともちゃんが何か大切なものをこつこつと貯金していくのをじっと見ていた。
お父さんが秘書にひかれていくのを見て、とてもとても傷つき、夜中に何回も寝返りをうったともちゃんの胸の痛みを、丸く縮こまった背中を。小さいときには一緒に遊んだ場所で、幼なじみの欲望に打ちのめされたともちゃんの感じていた、固く嬉しくない地面の感触を、そのあとひとりで歩いて帰るともちゃんのぼうっとした悲しい顔を。
そして、お母さんが死んだとき、最高に孤独な闇の中でさえ、ともちゃんは何かに抱かれていた。ベルベットのような夜の輝き、柔らかく吹いていく風の感触、星のまたたき、虫の声、そういったものに。
ともちゃんは、深いところでそれを知っていた。だからともちゃんはいつでも、ひとりぼっちではなかった。
よしもとばなな. ともちゃんの幸せ. (文春文庫「デッドエンドの思い出」所収 p.178-179.)