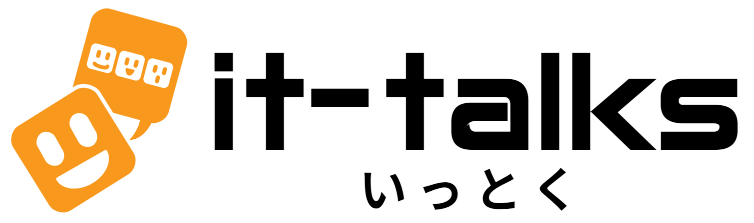父は若いころ結核で死にかけたそうだ。療養所に入ったが、そこにいたって病状は好転しないと確信したかれは、ある夜荷物をまとめて逃亡した。そして、どこから仕入れてきたのか、結核を治すには毎朝冷水を浴びるがよろしい、という情報を得て、毎朝かかさず風呂場にはいり手桶に汲んだ冷水をザーザー、ザーと頭から浴びていた。結核になったのは結婚前のことだったが、結婚して子どもが生まれてからもずっと、真冬の寒さにもへこたれず毎朝水を浴びていた。ザーザー、ザー・・・・・・肺炎になったあとも、その悪い生活習慣をあらためなかったので、子どものわたしでさえ呆れていた。
父が45歳のとき、かつて結核で最初に入院した慶應病院から一通の問い合わせの葉書がとどいた。「病院は、藤本和平の死亡した年月を報告せよと要求しているんだ」とかれは笑っていった。
父が87歳で死んだ朝、わたしは病院に泊まっていた。長椅子で仮眠していたわたしはなぜかはっとして目が醒めた。そうしよう、と考えたわけではなかったが、わたしは父のベッドに駆けよりようすを見ると、とても苦しげに浅く呼吸をしていた。30秒ほどたっただろうか。父の呼吸はとまった。「おとうさん、おとうさん」と大声でいってみたが、苦しみの去ったおだやかな少年みたいな顔になったかれはもう息はせず、黙って目を閉じていた。わたしに聞こえたのは、「こういうこと? これだけのこと?」といっている自分の声だけだった。
あれは無音の時刻だった。究極的な無音の時刻だった。無音の空間に生と死の境界線が黒々と引かれた。
monkey business. Vol.8. 音号. 音のひとり歩き. 藤本和子. 2010.1. p.205-206.