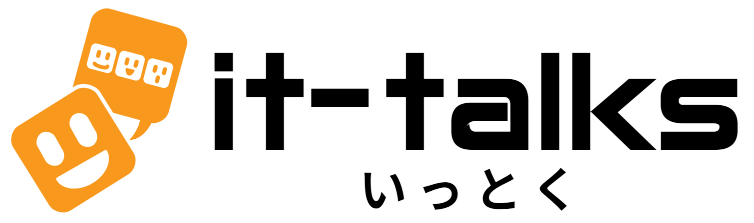何年か前、父親が病院で亡くなった時、その傍には誰もいなくて、翌朝駆けつけると、父親は哀しそうに目を開いたままで、弟が手で目をつぶらせた。肩の荷が下りた、という気しかしなかった。
それから何年かたって、東京駅で倒れて一週間、集中治療室にいた母親が意識を回復することもなく亡くなった。ぼくと弟の家族が見守ったのだが、ぼくも弟も、ただぼんやりしていたように思う。
『いのちつぐ「みとりびと」』は、國森康弘さんの写真集。國森さんは、滋賀県の小さな集落の人々の暮らしを追いかけてきた。いや「暮らし」ではなく、どんな風に、亡くなっていくかを追いかけた。その小さな共同体では、老いた人・死に近い人のケアに全力が注がれる。「死」が大切なもの、愛しいものとされていた。小学校5年の女の子の大好きな「おおばあちゃん」が亡くなる。女の子の瞳から涙がこぼれる。けれども、最後に女の子は、「おおばあちゃん」にキスをしてお別れする。強い印象を与えるのは、死者に寄り添うその家族たちの、明るい笑いだ。「生ききった家族」を見送る視線の明るさだ。
この写真集には、たくさんの「遺体」が写っている。でも、暗くも怖くもない。見ていると、心が穏やかになり、優しい気持ちが溢れてくるのがわかる。うらやましいと思う。そんな場所に住みたい、そんな家族の一員で有りたいと思っている自分を発見して、ぼくは驚く。
多くの人たちは、最後は病院で死ぬものだと思っている。「死」は家から隔離されるものだと思い込んでいる。そして、そんな生き方を、ほんの少し、淋しいとも感じているのである。
高橋源一郎. 一から創り出すということ. 朝日新聞朝刊. 6/28. p.17.