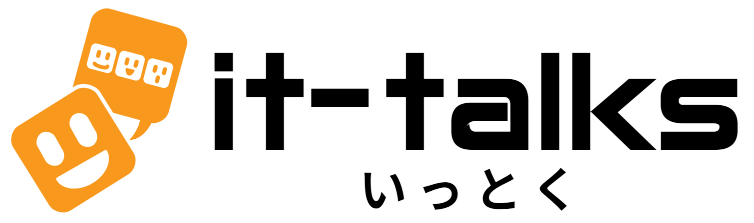民さんこれ野菊が、とぼくはわれしらず足をとめたけれど、民子は聞こえないのか、さっさと先へゆく。ぼくはちょっとわきへものをおいて、野菊の花をひとにぎり取った。
民子は一町ほど先へ行ってから、気がついてふりかえるやいなや、あれっと叫んでかけもどって来た。
「民さんはそんなにもどって来ないだって、ぼくが行くものを……」
「まあ、政夫さんはなにをしていたの。私びっくりして……まあきれいな野菊、政夫さん、私に半分おくれったら、私ほんとうに野菊が好き。」
「ぼくはもとから野菊がだい好き。民さんも野菊が好き……」
「私なんでも野菊の生まれ返りよ。野菊の花を見ると身ぶるいのでるほど好もしいの。どうしてこんなかと、自分でも思うくらい。」
「民さんはそんなに野菊が好き……道理でどうやら民さんは野菊のような人だ。」
民子は、分けてやった半分の野菊を顔に押しあててうれしがった。ふたりは歩き出す。
「政夫さん……私野菊のようだってどうしてですか。」
「さあ、どうしてということはないけど、民さんはなにがなし野菊のようなふうだからさ。」
「それで政夫さんは野菊が好きだって……」
「ぼくだい好きさ。」
(伊藤左千夫『野菊の墓』)