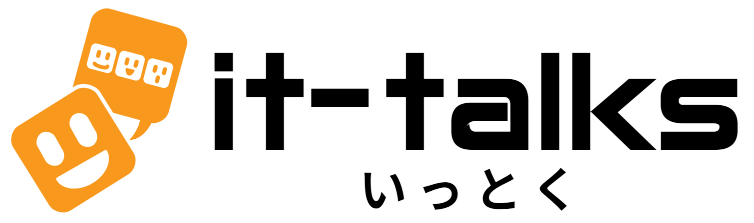【報告】ブリュノ・クレマン氏講演会「哲学者は作家か?」
http://utcp.c.u-tokyo.ac.jp/blog/2013/04/post-607/
「次にクレマン氏は自らの著作においても扱っている「方法の物語」を取り上げ、方法的物語も註釈と同様に、物語と理論、主体と抽象を召還し適合させる点で「主観的含み込み」を持つと述べる。例えばデカルトの『方法序説』はあらゆる分野、時代、学問の理論家たちが、いかなる仕方で方法を発見したかを物語るために書いたテクストであるが、そこで重要なことは、一人称単数の物語が、理論的で思弁的な目標を定めるということであるという。さらに氏はポール・リクールの『時間と物語』をあげ、物語は時間性と自己同一性を共に支えようとする二つのアポリアを持つことを指摘する。方法的物語は、抽象と普遍的なものの筋道と、個人的で主観的な経験の筋道とを同時に掴んでいるということは、本質的なアポリアであるという。それは、後に生じた物事を前提条件としてまかり通すという虚構であり、内心(intimité)において作り出されたものを普遍的なものとして通す虚構である。したがって、方法的虚構は必然であると同時に望まれざるものであり、時宜を得ないと同時に運命的であるということを認めなければならいのだという。」
「プラトン、ルソー、デカルト、ニーチェ、フーコー、レヴィナス、デリダ、その他多くの人たちは、きわめて傑出したプロソポペイアの遣い手たちであり、それゆえ、プロソポペイアは、哲学等の理論的言説の修辞学という問いのみならず、さらに深く、理論的言説と文学的ないし美学的創造の関係という問いを立てることを可能にする手段の一つなのである。実際にプロソポペイアとはまず直接話法であり、船、法、死人等の語ることができないはずの何者かが語ることをいい、それは虚構の談話でありまた道徳的談話でもあるのだ。結語として氏は、「抽象」あるいは「……から抜き取られた(abstrait de …)」という表現をあげ、他動詞的抽象化の概念を提唱する。それはまさに比喩形象における言語作用によって還元された思考であると思われる。抽象的で理論的でありつつも比喩として表現される限り虚構性を纏うこの言説は、哲学的でありつつも文学の虚構性からは逸脱することができないのである。真理への探求もまたこの虚構性に還元されると言えるだろう。」
このひとの本、翻訳されないかなあ・・・とりあえず、これはあるらしい
ベケットを見る八つの方法——批評のボーダレス
岡室美奈子・川島健編
http://www.suiseisha.net/blog/?p=2507
「「ところでこれは何の声?」 ブリュノ・クレマン(西村和泉訳)」
もひとつ講演会
リュノ・クレマン講演「もうひとつの声の必要― モーリス・ブランショとプロソポペイア(活喩法)」報告
http://kguramo.kanto-gakuin.ac.jp/modules/news1/article.php?storyid=80
「「プロソポペイア」とは、語源から言えば、「顔」ないし「仮面」(prosopon)を「つくる」(poiein)ということであり、(登場)人物を作り出すことを意味するが、修辞技法としては、その場にいない者、あるいは現実に存在しないもの、さらには生命をもたないものに声を与えることであり、クレマン氏はこの「声」という主題をとりわけ重視している。不在の者に声を与え、登場人物を作り出す、というと文学的テクストの特権のようだが、クレマン氏が注目するのは、実はこの文彩が、プラトンからルソー、そして現代の哲学者デリダに至るまで、哲学的・理論的テクストにも実に頻繁に見られるということである。実際、プラトンの『クリトン』やルソーの『学問芸術論』は修辞学においても「プロソポペイア」の典型例とされている。『クリトン』では獄中のソクラテスが、脱獄を勧めるクリトンに対し、「「国法」ならこう言うだろう」として「国法」に語らせ、国法を遵守する者として死を選ぶことになる。『学問芸術論』ではルソーが、古代ローマの執政官ファブリキウスがその後のローマを目にしたらこう言うだろう、という想定のもとで、ファブリキウスを生き返らせて語らせる。今回の講演は、このような文彩について、文学と哲学の閾で書き続けた文芸評論家・作家モーリス・ブランショ(1907-2003)のテクストを通して考察し、文学と哲学、のみならず、現実と虚構、自然と技術といった境界をも問い直そうとするものであった。以下、講演の概要をたどっておこう。
ブランショの主著『終わりなき対話』(1969)の第一部は、「複数的な話し言葉」と題されている。ブランショが一貫して関心を抱いているのは、「書かれた言語」である文学言語であるのだが、ブランショにとって、考察に価する文学言語とは「複数的な話し言葉」なのである。『終わりなき対話』には、プロソポペイアとみなすことのできる箇所が多々見出されるが(講演ではいくつかのプロソポペイアが分析された)、プロソポペイアとは、「複数的な話し言葉」を作動させる技法である。ブランショは、20世紀の作家のうちでプロソポペイアの精神を行為遂行的(パフォーマティヴ)にもっとも深くつきつめた者だといえよう。プロソポペイアにおいて顕現するのは、たんなる対話の相手ではなく、根本的な他者性を孕んだ声である。そしてこの声は、必然的に(先の『クリトン』や『学問芸術論』の例でもわかるように)虚構的な声である。以上から導かれるのは、少なくともブランショにおいて、その評論はある種の虚構性において小説から区別されないということであり、思考することは、ある虚構的な比喩形象(フィギュール)(「フィギュール」は「文彩」と同時に、「図像」や「顔」、「人物」を意味する語でもある)を召喚することにほかならないということである。」
これが、ものすごくわがものとして理解できるような気がするじぶん、というのがいて、それでほんとうにイイのだろうか? できている、というのではないんだけど、こういうのがやりたいんだよ、ていう意味で。
(キシュのテーマでもある。というところ等がワカルから、「合ってる」のだとはおもうのだけど、わたしのレベルが低すぎるんだよね、いかんせん)