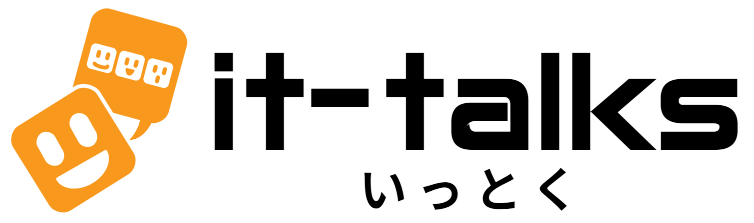http://h.hatena.ne.jp/florentine/299893770725412008
そして、おはなしを読むひと、ていうのは基本、内省というものをこそ日々の糧にするひとたちが多いはずで、
発散とかカタルシスとかそういうのを得るのは、ほとんどの場合は物語作法でいうとラストにしかない
その前に、十二分にいやったらしい気分を味わってもらうのがそもそも御馳走なんだよね(書くときはサドが鉄則っすw)
とはいえ小説というのは、たんにひとの支えになり、そのそばにいるもの、ていうだけではけっしてないし、
わたしはそういうものだけを書きたいとおもってるわけじゃない(ていうか、ほんとはもっとわたし、新しいこととか出来たらしたい、ウリポみたいなかっこいいこと! ただその才能がなくて、あと、合わないw)
ただ、
そういう「役目」がある程度はふられてはいる、てことは忘れない
わたしもまた、そういうものにすくわれているのだ
てのを、
「視界樹の枝先を揺らす」読み返してておもった
関係ないけど、いや、あるか
「あれは七月のことだった。短い梅雨に水不足が懸念され猛暑らしい日差しが照りつけていた。にもかかわらず呼び出しは常に戸外でその不満を漏らしていたころだ。」
今年みたいな気候のとき、だったのね
師匠と北の夢使いの出会った年、は
ここんとこ補遺の為によみかえしてるんだけど
このはなしがいちばん、自分としては出来がいいような気がする
すらすらって書いてる、絵がみえていたっていうとわかりやすい
距離の取り方、回想というのがこのてのはなしの形に嵌まりやすい、ていうのとテーマ性が絞られて過不足ないような感じで、異形の「視界」がちゃんと描かれている(やりたいことができた)ていう意味で
どうだろ?