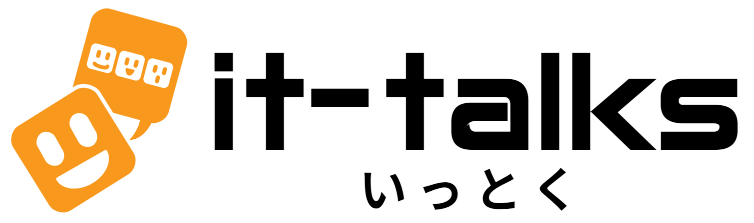3月24日 昼間
107
私は喉をおさえて、すとんと椅子に腰かけた。膝に、震えがきた。やっぱりミズキさんに何か言ってもらえばよかった、またはそばにいてほしいなんて考える自分がいた。びっくりだ。
「センパイ?」
ここで言うのがいちばんだと思った。察しろというのは酷だ。
その瞬間、どーん、という花火の音が頭上で弾けた。今になって思い出した。あの学園祭の夕方、頭の後ろで花火が鳴っていたとき、なんで泣きそうになったのか。
断って気まずくなるのがイヤだからとか、アサクラ君を勘違いさせた自分が恨めしかったからとか、そんなんじゃない。彼は絶対に自分の嫌がることをしないっていう期待が裏切られて、悲しかったからだ。
もう決めたのに、せっかく自分が覚悟を決めたのに、いつも、浅倉くんは決めたあとなのだ。酒井晃とつきあって半年、もうこれ以上拒むのは難しくて伸ばしに伸ばした年貢を納め、それでようやく安心したのか彼がとても優しくなったころだった。築地の交差点でも、私はあのすこし前、マリッジ・ブルーを乗り切ったと自分自身で確信した。それなのに、いきなりやってくる。
ああもう、ほんっとに腹の立つ!
「ミズキさんに指輪もらったから」
ほとんど勢いで言い切って、無意識に握りしめていた手をゆるめて電話を持ちなおした。
「私、昨日からずっと彼と一緒で、さっき、ミズキさんのお父さんにも挨拶した」
ようやく声が聞こえた。思ったより反応が鈍い。な、とか、え、とか言っている。
電話の向こうの気温は何度だろう。なぜかそんなことを考え、ごめんなさいとだけは口にしないと決めた。不意打ちとはいえ、珍しく私のほうが早い。
「いろいろ考えて、そのほうがいいって思って決めたのね」
「待てよ」
意外にもしっかりした制止に、私は笑った。
「待たないよ。私はもう、誰も待たない。ミズキさんに決めたの」
「なんで」
悲痛な声ではないし、あわててもいない。よくよく考えれば、彼は私のケイタイだけじゃなくて家にも当然、電話をかけただろう。ある程度、なんらかの予測はしたはずだ。ならば、正直にはなしてもいいだろう。
「ミズキさんのほうがほっておけないの」
「だから、なんでだよ」
「浅倉くんはひとりでもだいじょうぶ。ミズキさんは不安なの」
沈黙が落ちた。それにしても、こないだそう言ってふられた自分が、同じことを口にしていると思うとおかしい。
「浅倉くん?」
「聞いてるよ。続けて」
「続けてって……」
「まだ、言うことあるだろ。全部、吐き出せよ。どうせなんか、あいつに言われたんじゃないの。あんたがいないと死にそうだとか何だとか」
誘導されそうになって息を凝らした。
「結婚してくれないと生きてけないなんて脅すような男と一緒にいて、あんた、ほんとに幸せなの?」
心臓が、とととって嫌な感じに脈打った。そのまま、きゅうって縮まるような気がして、慌てて胸をおさえると、険しい声が聞こえた。
「あんた、ほんとうにバカだよ。あいつもだけど。好きな女、脅して怖がらせてどうすんだよ。そんな男と一緒になっても」
「そうじゃなくて」
遮るように否定すると、
「そうだろ」
強い声が返る。耳を塞ぎそうになりながら、私は精一杯、訴えた。
「それは……それは、違うの。ちゃんと私、そうやって彼に怒ったの。わかってるの。それは間違ってるって、ちゃんと私は言った」
今度こそ、彼は黙りこんだ。
「私ちゃんと、そこは言ったの。流されないで、きちんと反論して、聞き分けてもらったと思う」
ミズキさんだってほんとうはわかっているはずだ。なにが正しいか正しくないかとか、彼は考え尽くした。それと同時に、たぶん、三人のなかでいちばんに、この均衡をも考えただろう。彼がいちばん、考えることができる立場にいたはずだから。そして、それでも私を選ぶといったのだから。私はそれにこたえるしかない。こたえたいと、思う。
「それで……ミズキ、なの?」
そこにきて初めて、彼の声が揺れた。いつもの掠れ声が弱くなったような気がした。
「そうね」
「なんで、だよ」
「彼のほうが、それでもやっぱり、かわいそうだって感じるからじゃないかな」
ひとをかわいそうだなんて思うこと自体、驕り高ぶった厭らしい感情だということくらい理解している。でも、ミズキさんは自分でそれをよく知っていて、私にそこを晒してきた。弱みを見せないことくらい、彼ならいくらでもできただろう。
それに、浅倉くんだってきっと感じたことがあるはずだ。でなければ、同性相手にほっとけないなんて言わないと思う。
あまりにも静かになってしまって、私は鼻をすすりながら、昔の話をした。
「……学生の頃、来須ちゃんが、浅倉くんと付き合えって言ったんだよね」
酷く、戸惑っているようだった。そうだろう。私だって、こんなことを今さら白状してどうするのだと思ってる。でも、なんだか話したかったのだ。
「浅倉くんは邪魔されたって言うけど、ほんとはかなり真面目にすすめてたよ」
先輩には酒井先輩じゃなくてアサクラみたいな男のほうがいいんです。なんで。先輩がああだこうだ言うのにいちいち応答する頭があっちゃダメですから。それじゃつまんないよ。男ってのはつまるとかつまらないじゃなくて、とりあえずそこにいればいいんですよ、たまにちょこっと役に立つくらいで、もうそれ以上のことを求めるのは間違ってます、アサクラはそれができるから。
彼女のつぶやきに苦笑して、言い返した。
じゃあ自分でつきあえばいいのに。あたしはああいう男はダメです。どうして。見てるとイライラする。私もたまにするけど? それでいいんですよ、どうせアサクラは先輩に叱られるの待ってるんだから……。
来須ちゃんのお父さんが、彼女がまだ中学のときに出奔したと聞いたのは、卒業した後のことだった。抜群に成績のいい奨学生で、同じ英語学科の浅倉くんが要領よく単位を落とさない程度にさぼっているのを横目にして、きちんと講義に出ていた。私も真面目なほうだと自覚していたけれど、比べると恥ずかしくなるくらいだった。
どこか奇妙に異性に対して頑ななところがあって、大森くんと結婚するのも悩んだらしい。つかず離れずで、十年以上つき合っていた。踏み切れないんですよ、と自嘲する横顔をいくど見たかしれない。
「それ……今、聞いて、オレ、どうすりゃいいんすか」
情けない、半泣きの声だった。
「う、ん。そう、だよね。ごめんなさい……」
謝る予定はなかったはずなのに、私も泣きながら頭をさげていた。机につくほどさげた頭に血が落ちていくのは、けっこう気持ちがよかった。
「オレだって……」
落ちこむし傷つくんだよ。こわいんだよ、たかがふられたぐらいで、と彼は続けなかった。それはもう先月、聞いた。知っている。
「なに」
「……や、なんでも、ないです」
最後のほうは、小さくなった。電話から顔をはなしているらしい。
「浅倉くん?」
「ハイ」
「伝言、聞いたよ……」
ありがとう、と言うつもりでいたのに言えなかった。震える唇を右手でおさえると、堰きとめられた熱が指を濡らした。それがあんまりあふれてきて、気持ち悪くて、あわてて立ち上がりバッグからハンドタオルを取り出した。右手にケータイを持ち替えても、まだむこうから言葉になるほどの音は聞こえてこなかった。
浅い息継ぎが耳をうつ。
「あれ……すごく、うれしかった」
そんなこと言うなよ、とは叱られなかった。ただ、いくらか呼吸が乱れて、鼻をすする音がした。ティッシュないの、と言いたくなったけど黙っておいた。泣き顔がみれないのは残念だと思う自分に喝をいれて、お別れの言葉を用意した。
「いつ、帰ってくる?」
ん、と喉にからんだ声を直すようにしてから、浅倉くんらしい屈託のなさでこたえてくれた。
「明日か、明後日の午前には戻ります。月曜昼には、六本木にいないとならないんで」
「そっか。じゃあ来週あたり、龍村くん誘ってお花見でもしようよ」
それいいっすねとの返事にかぶせ、じゃあ、気をつけてね、と電話を切った。
ありがとうとさよならのつもりでお辞儀をした。ゆっくりと半身をおこし、右手のなかで熱をもっている携帯電話を閉じてテーブルにおく。それから、机にぺたりと腕をついてそのうえに顔を伏せた。頬に触れた木の感触が冷たくて心地いい。
花見と花火、か。音も似てて、一字違いじゃん。しかも、どちらも見あげるものだ。
ふ、と唇に浮かんだ笑み。
笑えるなら、だいじょうぶ。
上から見る花火が綺麗だって聞いたことがある。今年は悔しいから、両方、どっか高いところから眺望しよう。
見渡してやる。この世の全部、いつか絶対、見渡そうと、なぜだか挑戦的な気分になっていた。
遍愛日記のことを語る