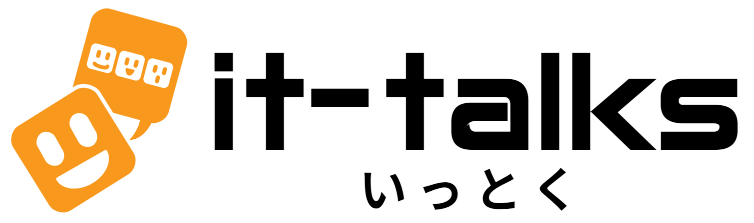3月25日
127
それにはぎょっとして私が息をつめたので、彼は笑って、仕事のことだよ、あいつ社長だし、とこたえた。私もミズキさんに口で勝てると思っていない。というか、腕力でも、申し訳ないけれどこのひょろっとした浅倉くんのほうが強いとは思えない。
俄かに不安になってうつむくと、頤を指でつままれて顔をあげさせられた。
「だいじょうぶ。今まで一度も、あんたの命令、失敗したことないじゃん」
「そう、だけど……」
「ちなみに、ミズキの命令にも逆らったことない。完全絶対服従なんだよね」
目をしばたくと、彼は右手でバッグの中を探った。いいかげんに落とし込んだだけだからすぐに、鍵が二つ、ぶらんと出しっぱなしの青いキーケースが目の前にさしだされる。
「誤解してるようだから言っとくと、オレの友達に似てるのは、ミズキじゃなくてあんたのほう。ちっさくて色白くて骨細くて、すごく脆そうにできてるのに弱くない」
私は息をのんで、そう言った相手の顔を見た。怯えた様子もなく希う卑屈さもなく、挑戦的にこちらを見ていた。その視線に怯むいわれもなくて、両目を見据えた。
「オレのこと、怖くない?」
それにしても自惚れている。それとも私をなめてるのか。だいたい私がコワイといったらやめるのか。やめてくれるなら泣いてそう言う。でも、ここで泣いても逆に妙な刺激を与えるだけで、それを理由に覆いかぶさってきてなし崩しに好きなようにされるのは目に見えている。鍵はもう、とられちゃったんだから。
「オレが開けて、そのままオレのせいにしてもらったほうがほんというと気が楽。ミズキになに言われても、オレが無理やりしたからって言える。けど、それを抜きにすれば、あんたが開けてくれたほうがうれしい」
なるほど、そうだろうな。
肩で一息ついたあと、帯のうえあたりにぶらさがった鍵を手につかんだ。その瞬間、頤をつかまれたままでキスされた。それは外でするんじゃなくて、と思ったところで、彼は鍵を奪っていった。あ、という間で抗議の声さえ飲み込まれた。
くるりと視界が回転して暗くなった。
なんてことだ。いいように騙されてるじゃないか。なんだかとても悔しくて肘にバッグをかけたまま両腕で押し返そうとすると、相手はすぐに身体をひいた。後ろ手に錠をまわし靴箱のうえに鍵を置いた横顔に、ひどいと文句を投げつけると妙に楽しげに目を細めている。
「オレ、ずうっとあんたに、ヒドイって涙目で言われてみたかったんだよね」
「なっ……」
「酷いことされたら生きてるかぎりずっと復讐してくれるんでしょ?」
何されちゃうかすげー楽しみ、とにやけ顔で続けられた。私はまたうっかり、ヘンな生き物を家にあげてしまったと感じて額に手をあててうなだれていると、浅倉くんは私の手からバッグをとって靴箱のうえにおき、両腕をそっと帯の後ろにまわしてきながら、口にした。
「こんな緊張したこと今までないかも」
顔をあげると、目をそらされた。ずいぶんたくさん経験があるようで、と嫌味を思いついたけれど、喜ばせるだけだと思ったので黙っていた。
「まじ、やばいかも……」
また、小さな声がおりてきた。さっきまでの強引さがウソのように弱気になっている。なんだかなあ、と思いながらきいてみた。
「こういうのに失敗ってあるの?」
「や、その……」
「ああ、たたないとか?」
「それは、今んとこ、ナイ」
手をつかんで押しつけようとするので、それは頭をふって遠慮した。なんにもしてないのに、なんでそんなとこ反応させてるのかわからない。謎だ。
「え、オレの触るのイヤ?」
あんまり情けない顔をするので笑いをかみ殺しながら首をふると、なんだ、やっぱりあんたのほうが余裕じゃん、と拗ねてみせた。
いや、べつにそういうわけでもないし私もかなり緊張してるのだとわざわざ説明してあげるほど優しくはないので、かわりにずっと謎だったことを思いきって尋ねてみた。
「浅倉くん、前から不思議なんだけど、なんで私がこわいの?」
「好きだから」
「私も浅倉くんが好きだけど?」
そういうと、うわあ、と叫んで離れた。ここは抱きしめるところじゃないかと思うのだが、リアクションがずれる。
「や、でも、オレのほうが絶対ものすごい好き。もうそれは間違いない。だから、どうしても弱いっつうか立場ないっつうか、さっきだってあんなこと言ったけど、ほんとはあんたにカッコ悪いとこ見せて呆れて嫌われたらどうしようっつうか……」
「みんなよく、そう言うんだけどさあ」
どうもそこが、私には納得いかないのだ。
「好きなほうが、強くない? だって、それって誰からも奪えないよ? しかもそれ、最強カードでしょう。さっきみたいに好きなら何してもいいって言えるし、自分のなかの真実だもの、動かしようがない。
それに私、今までつきあったひと、一度も自分からふったことないし、べつに浅倉くんをかっこいいって思ったことそんなにないから、セックスでもなんでも、いいとこ見せようとしなくていいよ。そんなんで嫌いにならないから」
私の言葉のなにがショックだったのか、彼は目を見開いていた。もしや正直に語りすぎたかと首を傾けると、なにか楽しそうに小さく喉を鳴らしている。
「浅倉くん、ついでに言うと、私が褒めておだててあげないといけないなら正直すごくめんどくさいし、それでもどうしてもそうして欲しいって言われればどうにか頑張るけど、上手にできる自信はあまりない。今までちゃんとできたためしないし」
「え、え?」
「それからね、浅倉くんがそうなように、私もすごくかっこつけたいの。弱くてずるい自分を知ってるからこそ、そこを見せろって強制されるのはすごくイヤなの。ただでさえしたになって」
「オレが下でもいいよ」
そんなとこだけ反応が早くて呆れていると、彼も自分でおかしかったみたいでうつむいて身体を小刻みに揺らしていた。
遍愛日記のことを語る