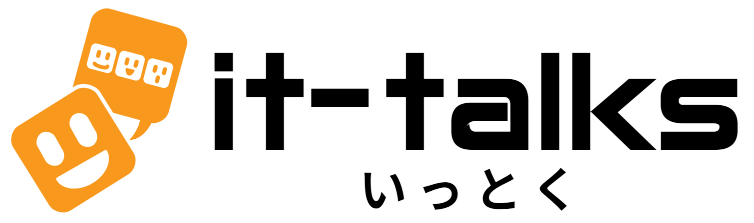審判の日 悔悛
186
彼が、柳眉を寄せた。
「違う? 彼から距離をとっておきたかったんじゃない? どっちに転んでもいいように」
「お見通しっていうわけ?」
「ミズキさんの考えることはわかるよ」
そう、なのだ。私には、彼の考えることは予測できた。それは、でも、彼が私に考えさせようとするからだ。
「ねえ、あの、嫌味とか皮肉とか拒絶とか、そういうんじゃなくて真面目に言うんだけど、ミズキさんだったら、私みたいな女じゃなくて、優秀な遺伝子もった女性と結婚して子孫にその能力を継承していったほうがいいんじゃないかなあ。もったいないよ」
もう素で、本気で口にしたのだけど、彼は苦々しい顔つきでいた。それからゆっくりと頭をふって告げた。
「そういう意味で言うなら、僕は、僕の持つもの全てで姫香ちゃんにだけ投資したい」
「それはミズキさんらしくない下手な戦略じゃないかな。もう年だし効率悪いよ。それに私、子供生むの怖い。この先の地球で子育てするのもこわいしちゃんと育つか心配だし、自分の遺伝子が残ること自体がなんだか気味が悪い」
「姫香ちゃん……」
「子供欲しいと思うこともあるんだけど、コワイ。妊娠するのも出産するのも育てるのも自分にちゃんとできるような気がしないし、私、子供の頃からお嫁さんとかお母さんになりたいって一度も思ったことないの。なんでかわかんないけどそういうふうに思ったことないから、結婚とかむいてないと思う」
「でも君」
「うん。結婚はしたかったの。それはでもね、人並みになりたいっていうことで、子供もきっとそういう意味でしかなくて、ひとと同じで安心したいっていうことでしかないと思う。私は私が大好きで大嫌いだから、子供もきっとそうなっちゃいそう。自分のことを許して愛せるようにならないと、子供に過剰な期待をかけたり色々しちゃいそう」
涙が出そうになった。
「そういう私でもいい? 私、きっと子供、生めない。だけとミズキさんの遺伝子、絶対もったいないと思う。でも私、浮気されたらすごくイヤだろうし、矛盾してる」
「僕に……執着してくれるの?」
彼は私の問いかけじゃなく、べつの場所に反応した。
「君に、こんな酷いことするような人間にこたえてくれるの?」
ミズキさん……。
確認と呼ぶよりは、懇願に聞こえた。そして、そういう私の表情を瞬時に見抜いて瞳を伏せて、返答がないことで私の顔をのぞきこむ。それはきっと、彼の幼いころの習い性だった間の取り方で、私はそれを知っていしまっている。
「……悪いことしてるって自覚があるなら、治せるでしょ?」
私は甘いかもしれない。そうも、思う。でも、私自身のなかにも支配ではなく、対等の関係でのレンアイの記憶がない。理想のストックがないのだから実現するのに困難を極めることは必定だけど、でも……それを、やっていったほうが、いい気がする。
「僕は……」
「ねえミズキさん、ほんとは話が逆だよね? 私は、自分が思ってる以上にずっと自尊心が強い。今の今までわかってなかったけど、私はミズキさんが私という人間に全面降参してるから受け入れたんだと思う。そういう私の支配的な関係で、ミズキさんこそ、我慢できるの?」
そんなどうしようもない問いかけにさえ、一瞬の間もなくこたえが返る。
「何度も言うようだけど、僕は、どうしてか、君じゃないと駄目なんだよ」
そう、なんだろうね。
ほとんど泣き笑いのような顔へと頷いた。
「それじゃあ、ちゃんと優しくするから」
おいでと手招きする前に抱きついてきた相手を抱き返す。こんなところで大のおとながふたりして抱き合って泣いているのはおかしいと、どこかで醒めた思考の片隅で感じ、情けない気分でぼやきそうになっていた。恋愛とか結婚って、もっとなんだか光輝溢れる素晴らしいものだと思っていた。これじゃあんまりにも格好が悪いけど、でも、現実はこんなものだ。
涙が染みになると嫌だなあと思いながら、私はその広い背を撫でた。こんなに大きくて立派なのに、鍛えているというだけあってちゃんと筋肉質なのに、どうして私みたいなちびちゃいひとに抱きついて大泣きするかなあ、と不思議だった。
けれど、両腕であやすようなつもりでかきいだいて、ああ、このひとはきっと浅倉くんの前では泣けないのだと気がついた。泣きたくても、浅倉くんはそれを許さない。許しそうなくせに、彼にはそうしない。手を引っ張って、立たせようとしているのだ。彼ならできるだろうと期待し、励ましている。
それもきっと、正しいやり方だ。
私はこのひとを哀れなお姫様のように思っていて、でもそれはきっと、一面的な見方でしかない。彼が自分で言うように、期待されるのが好きで張り切るところもたくさんあるのだ。それだけじゃなくて、自分の欲望を押し通そうとするだけの強引さと図太さも人並み以上に持っている。
私だっておんなじだ。
ミズキさんの前では王子様よろしく、格好をつけて弱みを見せずにやり抜こうとしている。できているかどうかはともかく、私が自分に望む姿はそうで、このミズキさんもおそらく、あまり自分にしなだれかかってこない少年ぽく気の強い私が好きなのだろう。もっといえば、そういう私がたまに見せる弱さが快感なのかもしれない。
でも、私は浅倉くんの前では無意識にでも甘えてしまう。相手任せで流される心地よさに浸り、自分で決めなくていい安楽さにおぼれている。それでいて、最後のさいごで突っぱねるのだ。助けてと言い、どうにかしてと頼みにして、やっぱりそれはイヤだと自分で決めてしまった。
世の中そういうもの、か。
気がつくと、私の身体のうえで感情の爆発を終えた男はすこしはにかむように微笑んだ。ほんとに罪なくらい可愛い顔だった。かるく幾度か唇をあわせたあと、出ようか、と囁いた。けっきょくすることはしっかりするのだと呆れたけれど、ほんとうの理由は浅倉くんに会わせたくないのだとわかっていた。
「待って。電話だけさせて」
それでもずいぶん卑怯なやり方だと思う。だいたい出るのかわからない。しかも、仕事中にこんなこと聞かされたら最低だ。でも、そのくらい最低最悪なことを仕出かさないと、私も思い切れなさそう。かえってこれだけ酷いことすれば、なんだかすっきりする気がした。
「それはあとから僕がするよ」
「打ち合わせ終わるのは何時なの?」
非常識をするなと止められたのだと思っていた。すると彼は切なげに眉を寄せた。
「姫香ちゃんにもうこれ以上、辛い思いをさせられないよ」
今になって、そんなふうに思いやられていた。
「つらくないよ。ハッキリしたいの」
「強がらないでいいから」
「自分でしたいの。強がってるのかもしれないけど、今度こそ自分で言いたいの」
「僕にもたまには男らしいことさせてよ」
おふざけに紛らわせて本音を告げようとした相手に、私は一笑して返す。
「そういうヒロイズムはべつのところで発揮して。その点に関して、私は金輪際ひとを信用しないことに決めたの」
そうしてバッグを持ち上げたところだった。
お店のドアが軋む音がして、トッ、トッというやや堅い奇妙な、ぎこちない足音が耳に届いたのだ。